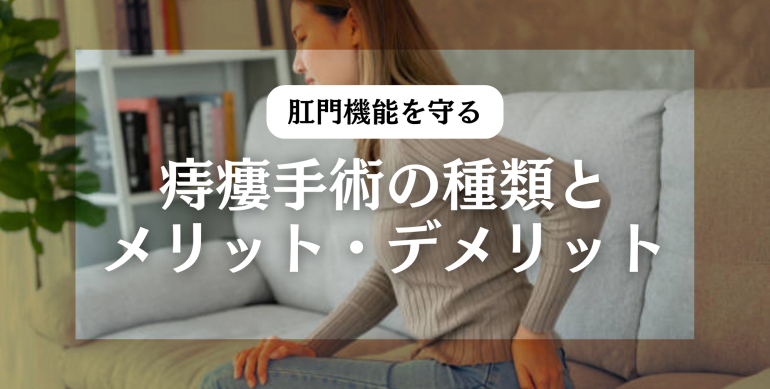
痔瘻(じろう)は、肛門周囲に炎症が起こり、膿がたまったあとに瘻管(ろうかん)と呼ばれるトンネル状の通り道ができてしまう疾患です。完治には手術が必要で、主に4つの治療法があります。
それぞれの手術法には特徴やメリット・デメリットがあるため、手術を受ける前にしっかりと知識を持っておくことが大切です。
今回は、痔瘻の主な手術方法について、わかりやすくご紹介します!
① 開放術(かいほうじゅつ)
「開放術」は、痔瘻のトンネル(瘻管)を切り開いて排膿・治癒を促す方法です。
この治療法の最大の特徴は「根治性の高さ」。再発のリスクが低いため、多くの患者さんに選ばれています。
ただし、瘻管の位置によっては、肛門の筋肉(括約筋)を切開する必要があり、その影響で一時的に肛門の締まりが弱くなることもあるため、慎重な判断が求められます。
② くり抜き法
「くり抜き法」は、瘻管部分だけをきれいに取り除く手術です。
括約筋をできるだけ温存することができるため、排便機能への影響が少なく、肛門機能を守る点が大きなメリットです。
ただし、完全に取り切れなかった場合は再発する可能性があるため、定期的なフォローが重要になります。
③ 括約筋温存開放術
括約筋温存開放術は、開放術とくり抜き法の“いいとこ取り”の治療法です。
筋肉を温存しながら、瘻管をしっかり除去することで、再発のリスクを減らしつつ、肛門の機能も守ることができます。
術後の生活の質(QOL)を重視したい方には、最もバランスの取れた方法といえるでしょう。
④ シートン法(Seton法)
「シートン法」は、瘻管にゴム紐や糸を通し、少しずつ締めていくことで安全に切開を進める方法です。
括約筋を一気に切らず、少しずつ段階的に治療していくため、筋肉の損傷を最小限に抑えることができます。
通常、1~2週間ごとに糸の締め直しを行いながら治療を続け、数ヶ月での完治を目指します。ただし、締め直しの際に多少の痛みや違和感を感じることがあります。
手術後の生活について
手術後は、日帰りで終わるケースもありますが、しばらくの間は通院が必要です。
また、術後は刺激物の摂取を避け、消化の良い食事を心がけることが、早期回復へのポイントです。
排便時の痛みや違和感がある場合もありますが、ほとんどは時間とともに軽減していきます。
まとめ
\ あなたに合った治療法を医師と一緒に選びましょう /
痔瘻の手術にはいくつかの選択肢があり、それぞれに特徴があります。
再発を防ぐために大切なのは、「自分の痔瘻の状態に合った手術法を選ぶこと」です。
不安や疑問があれば、遠慮せず医師に相談し、納得したうえで治療に臨みましょう。
しっかりと情報を持っておくことで、安心して手術を受けることができますよ😊
監修医師 大柄 貴寛
国立弘前大学医学部 卒業。青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、日本屈指の高度な専門施設、クリニックで消化器内視鏡・外科手術治療を習得後、2020年10月大田大森胃腸肛門内視鏡クリニック開院、2024年12月東京新宿胃腸肛門内視鏡・鼠径ヘルニア日帰り手術RENA CLINIC開院。





















