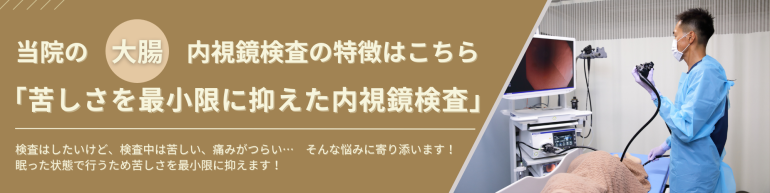1. 下血とは?便の色でわかる出血部位のヒント
 「下血(げけつ)」とは、胃や腸などの消化管から出血し、それが肛門を通って排出される状態を指します。多くの場合、便と一緒に血が出ることで気づかれ、「血便」とも表現されます。
「下血(げけつ)」とは、胃や腸などの消化管から出血し、それが肛門を通って排出される状態を指します。多くの場合、便と一緒に血が出ることで気づかれ、「血便」とも表現されます。
出血の色によって、出血している部位のおおよその見当がつきます。
-
・鮮やかな赤い血が便に付着している場合は、痔や裂肛など、肛門に近い部分からの出血が疑われます。
-
・**暗赤色や黒っぽい便(タール便)**の場合は、胃や十二指腸、小腸のような上部消化管での出血の可能性があります。
-
・便全体に血が混じっている場合は、大腸や直腸など、比較的奥の部位からの出血が考えられます。
出血が少量でも、「見た目だけで自己判断する」のは危険です。とくに、腹痛やめまい、倦怠感などの全身症状を伴う場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。
2. 下血の主な原因と特徴
下血の原因にはさまざまな疾患があり、その中には命に関わる重大な病気も含まれます。よくある原因は以下の通りです✓
-
✓ 痔核(いぼ痔)や裂肛(切れ痔):排便時に鮮血が出やすく、便器やトイレットペーパーに赤い血が付くことがあります。
-
✓ 大腸ポリープ・大腸がん:進行すると血便が見られることがあり、早期では出血が唯一のサインということも。
-
✓ 潰瘍性大腸炎・クローン病などの炎症性腸疾患:腹痛や下痢とともに出血を伴うことが多く、慢性化するケースがあります。
-
✓ 感染性腸炎:細菌やウイルスの感染による炎症で出血することがあります。
-
✓ 胃・十二指腸潰瘍:出血が腸を通って便に混じり、タール便として現れる場合があります。
年齢や家族歴(大腸がんの既往など)によってもリスクが変わるため、40代以降の方や不安がある方は、早めに消化器内科で相談しましょう。
3. 下血を見つけたときの初期対応
 もしトイレで下血に気づいたら、まずは落ち着いて状況を確認しましょう。
もしトイレで下血に気づいたら、まずは落ち着いて状況を確認しましょう。
-
・血の色(鮮血か黒色か)
-
・便との混ざり方
-
・出血量(滴る程度か、大量か)
-
・その他の症状(腹痛・立ちくらみ・発熱など)
これらの情報は、医師の診断に非常に役立ちます。
特に黒い便(タール便)や、大量出血、立ちくらみ、意識がぼんやりするといった症状がある場合は、すぐに救急受診してください。
一方、明らかに痔などによる少量の出血であっても、便秘や排便時のいきみが原因となっていることもあるため、水分や食物繊維を増やすなど、生活習慣の見直しも重要です。自己判断せず、必要に応じて肛門科・消化器内科を受診しましょう。
4. 受診すべき診療科と検査の流れ
下血を起こした際にまず相談すべきは「消化器内科」または「肛門科」です。出血の原因を特定するためには、専門的な検査が欠かせません。
受診時に行われる主な検査は以下の通りです:
-
問診:出血のタイミング、便の状態、体調変化など
-
肛門診(直腸診):痔や裂肛の有無を確認
-
血液検査:貧血や感染の有無を調べる
-
内視鏡検査(大腸カメラ・胃カメラ):出血部位の特定、ポリープや潰瘍の確認
検査は予約制のこともありますが、当院では日帰り内視鏡検査やオンライン予約に対応しており、必要に応じてその日のうちに内視鏡を受けることも可能です。緊急性が高い場合は救急外来を受診し、即時入院や処置が行われることもあります。
5. 放置は危険!下血のリスクと予防法
「ちょっと血が出ただけだから…」と放置してしまうと、思わぬ事態を招く可能性があります。
-
・大腸がんや胃潰瘍など、命に関わる病気が隠れていることも
-
・出血の繰り返しにより貧血や体力低下を招く
-
・早期に発見すれば軽症で済んだものが、入院・手術の対象になることも
下血を防ぐために、次のような日常生活の工夫が有効です
-
・食物繊維を意識したバランスの良い食事
-
・十分な水分摂取
-
・ストレスや睡眠不足を避け、腸内環境の安定
-
・年1回の大腸内視鏡検査(特に40歳以上や家族歴がある方)
異常を感じたら、我慢せず専門医に相談することが、健康を守る第一歩です。当院でも下血や消化器の不調についてのご相談を随時承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
監修医師 大柄 貴寛
国立弘前大学医学部 卒業。青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、日本屈指の高度な専門施設、クリニックで消化器内視鏡・外科手術治療を習得後、2020年10月大田大森胃腸肛門内視鏡クリニック開院、2024年12月東京新宿胃腸肛門内視鏡・鼠径ヘルニア日帰り手術RENA CLINIC開院。