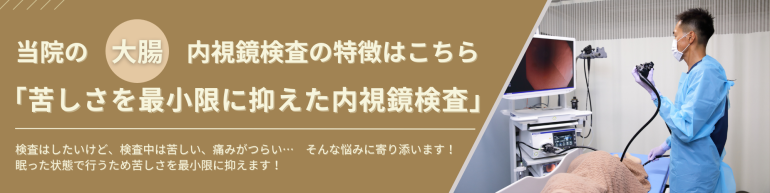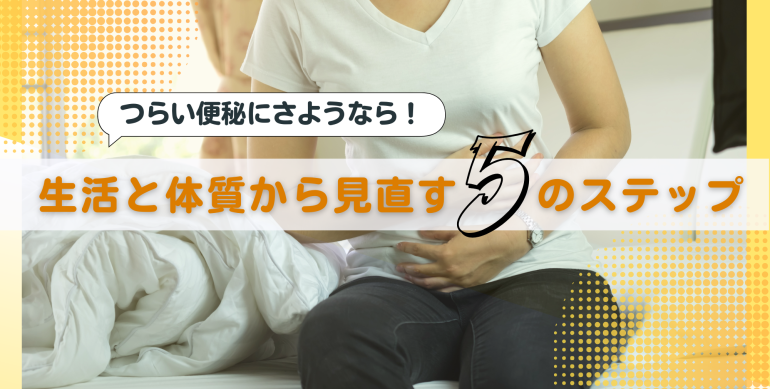
1. そもそも便秘とは?種類とその見分け方
 便秘というと「排便がない日が続くこと」と思われがちですが、実はそれだけではありません。日本消化器病学会では「排便回数が少ない」「排便時に強くいきむ」「便が残っている感覚がある」なども便秘の症状と定義しています。
便秘というと「排便がない日が続くこと」と思われがちですが、実はそれだけではありません。日本消化器病学会では「排便回数が少ない」「排便時に強くいきむ」「便が残っている感覚がある」なども便秘の症状と定義しています。
排便が週に3回未満、もしくはスッキリ出ない感じが続く場合は便秘と考えられます。
また、便秘には大きく分けて次の3つのタイプがあります:
-
「弛緩性便秘」:腸の動きが弱く、便が停滞するタイプ
-
「けいれん性便秘」:ストレスなどで腸が過敏に動き、スムーズに便が進まない
-
「直腸性便秘」:便意を我慢することで便が直腸に溜まりすぎる状態
自分のタイプを知ることは、適切な対処の第一歩です。慢性的な便秘には、消化器疾患など重大な病気が隠れていることもあるため、油断せず対策を取りましょう。
2. 便秘の原因は?見直したい生活の落とし穴
便秘の主な原因は生活習慣にあります。食物繊維不足、水分不足、朝食を抜く、運動不足といった要素は、腸の動きを低下させてしまいます。また、ストレスや睡眠不足、自律神経の乱れも便秘を悪化させる要因になります。
女性はホルモンバランスの影響を受けやすく、生理周期や妊娠、更年期などの時期に便秘が悪化しがちです。高齢者の場合は筋力の低下や薬の副作用が関係することもあります。
近年では、腸内細菌のバランスも便秘に関係することが分かっており、発酵食品など腸内環境に良い食品を取り入れることも有効です。
3. 今日からできる!便秘を改善する生活習慣
 便秘を改善するために最も効果的なのは、日常生活の見直しです。
便秘を改善するために最も効果的なのは、日常生活の見直しです。
-
・朝食をしっかりとる:腸の動きを活性化させる
-
・朝起きたら水を飲む:腸のぜん動運動を促す
-
・食物繊維を積極的に摂る:野菜、果物、海藻、豆類など
-
・適度な運動を取り入れる:ウォーキングやヨガがおすすめ
-
・便意を我慢しない:排便習慣をつける
-
・十分な睡眠をとる:自律神経を整える
どれも簡単に始められるものばかりです。まずはできることから1つずつ取り入れてみましょう。
4. 便秘薬の正しい使い方と注意点
 便秘薬はつらいときに助けになりますが、使い方を誤ると長期的には逆効果です。
便秘薬はつらいときに助けになりますが、使い方を誤ると長期的には逆効果です。
主な便秘薬には以下のようなタイプがあります:
-
・刺激性下剤:腸を直接刺激する。常用は避けるべき
-
・浸透圧性下剤:腸内に水分を引き込み便をやわらかくする
-
・膨張性下剤:便のかさを増やして排便を促す
最近では、ルビプロストンなど新しいタイプの処方薬もあり、体に優しく継続しやすい選択肢も増えています。薬はあくまで補助として、基本は生活習慣の改善が基本です。
5. それでも改善しないなら受診を
生活を見直しても改善しない、または以下のような症状がある場合は、医療機関の受診が必要です:
-
「急に便秘が始まった」
-
「血便が出る」
-
「腹痛や体重減少がある」
-
「便が細くなった」
消化器内科や便秘外来で、問診や内視鏡検査、大腸レントゲン、血液検査などを行い、隠れた病気の有無を調べます。放置せず、早期の検査と治療が重要です。
当院では、内視鏡検査から栄養指導まで、便秘改善のための総合的なアプローチをご提案しています。お気軽にご相談ください。
まとめ
便秘は体からのサインです。放置せず、食事・運動・排便習慣など日常生活を見直すことが改善への第一歩。必要に応じて便秘薬や医療機関のサポートを受けながら、自分に合った対処法を見つけていきましょう。当院では、医師と管理栄養士による個別対応が可能です。お気軽にご相談ください。
監修医師 大柄 貴寛
国立弘前大学医学部 卒業。青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、日本屈指の高度な専門施設、クリニックで消化器内視鏡・外科手術治療を習得後、2020年10月大田大森胃腸肛門内視鏡クリニック開院、2024年12月東京新宿胃腸肛門内視鏡・鼠径ヘルニア日帰り手術RENA CLINIC開院。