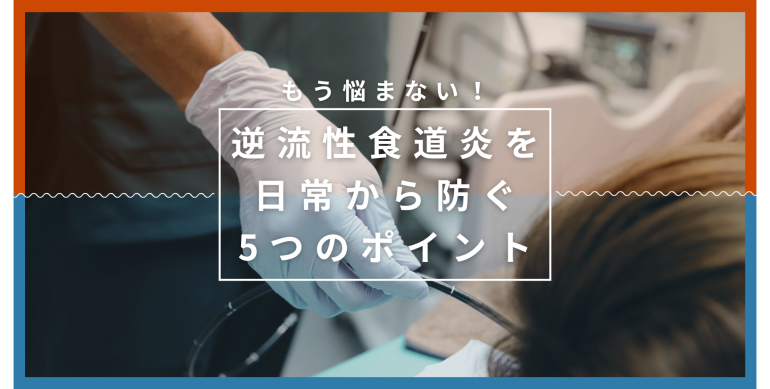
1. 逆流性食道炎とは?症状と原因を知ろう
 逆流性食道炎とは、胃の中にある胃酸や食べ物が本来は逆流しないはずの食道へ逆流し、粘膜を刺激して炎症を起こす病気です。代表的な症状には、胸やけや喉の違和感、酸っぱいものがこみ上げてくる「呑酸」、慢性的な咳、声のかすれなどがあります。
逆流性食道炎とは、胃の中にある胃酸や食べ物が本来は逆流しないはずの食道へ逆流し、粘膜を刺激して炎症を起こす病気です。代表的な症状には、胸やけや喉の違和感、酸っぱいものがこみ上げてくる「呑酸」、慢性的な咳、声のかすれなどがあります。
これらの症状が続くと、食事の時間が苦痛になり、日常生活の質(QOL)が大きく損なわれてしまうことも。
原因の多くは、胃と食道の境目にある「下部食道括約筋(かぶしょくどうかつやくきん)」の働きが弱くなること。加齢や肥満、妊娠、食べ過ぎ、姿勢の悪さ、さらにはストレスや食生活の乱れも大きく関わってきます。
この病気は生活習慣との関係が深いため、日々の小さな改善の積み重ねが、症状の予防や軽減につながります。
2. 食生活の見直しが第一歩
 逆流性食道炎の予防には、まず食生活の見直しがとても重要です。
逆流性食道炎の予防には、まず食生活の見直しがとても重要です。
避けたい食品としては、脂っこいもの、甘いもの、チョコレート、コーヒーや紅茶、アルコール、炭酸飲料、トマトや柑橘類などがあります。これらは胃酸の分泌を促進し、逆流を引き起こしやすくします。
また、食べすぎも要注意。胃の中の圧が高まることで、胃酸が逆流しやすくなります。食事は腹八分目を意識し、ゆっくりよく噛んで食べましょう。
さらに、食後すぐに横になると重力の影響で逆流しやすくなります。食後は最低でも1〜2時間は座った姿勢で過ごすことをおすすめします。
夕食は就寝の3時間前までに済ませるのが理想です。夜遅くの食事は控えましょう。
3. 日常生活で気をつけたいこと
 食生活だけでなく、日常の過ごし方にも注意すべきポイントがあります。
食生活だけでなく、日常の過ごし方にも注意すべきポイントがあります。
まず大切なのが「姿勢」。
猫背や前かがみは胃を圧迫し、逆流を引き起こしやすくなります。特に食後は背筋を伸ばし、リラックスした姿勢で過ごすことを意識しましょう。
また、きつめのズボンやベルトなど、胃のあたりを締めつける服装は避けるのがベター。圧迫によって胃酸が食道へ押し戻されてしまうことがあります。
さらに、激しい運動やジャンプを伴う動きは控え、ウォーキングやストレッチなど軽い運動を習慣にするのがおすすめです。
喫煙も要注意です。
タバコに含まれる成分は、下部食道括約筋の働きを弱め、逆流を起こしやすくします。逆流性食道炎の予防のためにも禁煙を検討しましょう。
4. ストレスと睡眠も大事なポイント
 胃腸はストレスの影響を強く受ける臓器です。ストレスや不安が続くと、自律神経のバランスが崩れ、胃酸の分泌が過剰になり、胃の働きも低下します。その結果、逆流性食道炎が悪化することがあります。
胃腸はストレスの影響を強く受ける臓器です。ストレスや不安が続くと、自律神経のバランスが崩れ、胃酸の分泌が過剰になり、胃の働きも低下します。その結果、逆流性食道炎が悪化することがあります。
ストレスを上手に発散することも大切です。例えば、散歩や音楽、趣味の時間、ゆったりとした入浴など、自分に合ったリラックス法を見つけましょう。
また、睡眠の質を高めることも予防には欠かせません。睡眠不足や不規則な生活は自律神経の乱れを引き起こし、胃腸の働きを悪化させます。寝る前のスマートフォンやカフェイン摂取を控えるなど、眠りやすい環境を整えましょう。
就寝時には枕を少し高くするなど、頭を上げた姿勢で寝ると、胃酸の逆流を防ぎやすくなります。
5. 予防のためにできることを継続する
逆流性食道炎は、継続的な生活習慣の改善がカギとなります。
一時的に症状が良くなっても、食生活や姿勢、生活リズムが元に戻ってしまえば、再発するリスクが高まります。
予防のためには、「無理なく続けられること」を日常に取り入れることが大切です。
また、市販の胃薬を自己判断で使い続けるのは避けましょう。
薬が症状を一時的に緩和することはあっても、原因を解決しなければ根本的な改善にはなりません。症状が続く場合は、医療機関に相談しましょう。
「少し変だな」「また同じ症状が出てきたな」と思ったときは、放置せず早めに対処することで、悪化を防ぐことができます。
まとめ
逆流性食道炎は、日々の食事や姿勢、睡眠、ストレスとの付き合い方など、生活習慣と深く関係しています。
脂っこい食事を控える、食後にすぐ横にならない、適度な運動を取り入れる、睡眠の質を高めるなど、特別なことではなく、誰でもできることから始めることが大切です。
症状が出てからの対応ではなく、「出さないため」の予防こそが、毎日を快適に過ごすための第一歩になります。今日からできることをひとつずつ取り入れて、健康的な生活を目指しましょう。
監修医師 大柄 貴寛
国立弘前大学医学部 卒業。青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、日本屈指の高度な専門施設、クリニックで消化器内視鏡・外科手術治療を習得後、2020年10月大田大森胃腸肛門内視鏡クリニック開院、2024年12月東京新宿胃腸肛門内視鏡・鼠径ヘルニア日帰り手術RENA CLINIC開院。




















