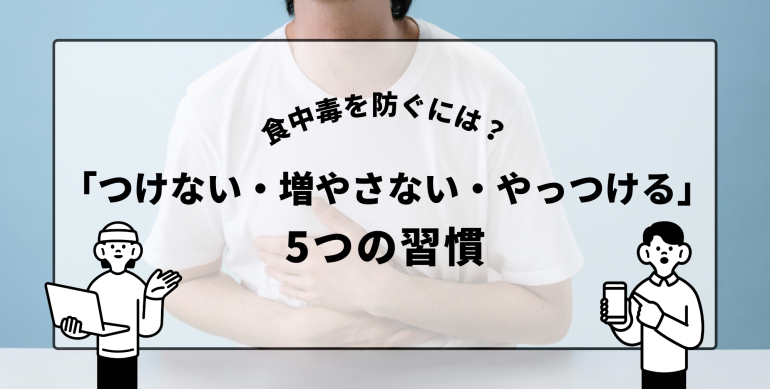1. 食中毒とは?原因と発生しやすい時期
 食中毒は、細菌やウイルス、または有害な化学物質が混ざった食品や飲料を口にすることで起こる健康トラブルです。代表的な症状には腹痛、嘔吐、下痢、発熱などがあり、体に大きな負担をかけることもあります。日本では特に気温と湿度が高くなる梅雨から夏場にかけて食中毒の発生が急増します。これは高温多湿の環境が、細菌やウイルスが繁殖しやすい条件を作り出すためです。
食中毒は、細菌やウイルス、または有害な化学物質が混ざった食品や飲料を口にすることで起こる健康トラブルです。代表的な症状には腹痛、嘔吐、下痢、発熱などがあり、体に大きな負担をかけることもあります。日本では特に気温と湿度が高くなる梅雨から夏場にかけて食中毒の発生が急増します。これは高温多湿の環境が、細菌やウイルスが繁殖しやすい条件を作り出すためです。
代表的な原因菌・ウイルスには、カンピロバクター、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌(O157など)、そしてノロウイルスなどがあります。これらは生肉や魚介類、卵などの食品を通じて感染することが多いほか、調理時の手指や調理器具の衛生管理が不十分な場合にも感染リスクが高まります。
特に日本国内で最も多い原因菌はカンピロバクターで、鶏肉の加熱不足が発症の大きな要因です。誰でもかかる可能性がある食中毒だからこそ、家庭での予防対策が何より大切です。まずは「なぜ食中毒が起きるのか」を正しく理解することから始めましょう。
2. 「つけない」菌を食品に付けないための工夫
 食中毒予防の基本は「つけない」、つまり病原菌を食品に付着させないことです。調理前後の手洗いは最も基本かつ重要なポイントであり、特に生肉や魚を扱った手で他の食品や調理器具に触ることは避けましょう。これにより菌が食品間で移動する「交差汚染」を防げます。
食中毒予防の基本は「つけない」、つまり病原菌を食品に付着させないことです。調理前後の手洗いは最も基本かつ重要なポイントであり、特に生肉や魚を扱った手で他の食品や調理器具に触ることは避けましょう。これにより菌が食品間で移動する「交差汚染」を防げます。
また、まな板や包丁などの調理器具は、生食材用と加熱済み食品用で分けて使うのが理想的です。特に鶏肉を切った後のまな板は他の食材に触れさせないように注意が必要です。食品を買ってきたらすぐに冷蔵庫に入れ、室温に長時間放置しないことも重要です。冷蔵庫内での保管時には、生肉や魚の汁が他の食品にかからないようにラップや密閉容器で覆う工夫も忘れずに。
これらの基本的な衛生管理を徹底するだけで、家庭内での菌の広がりを大きく抑えられます。
3. 「増やさない」菌の繁殖を防ぐ保存のポイント
病原菌は特に35〜40度の温度帯で急激に増殖します。つまり、食材や調理済み食品を常温で放置すると食中毒のリスクがぐっと高まるのです。買い物から帰ったら、冷蔵・冷凍が必要な食品はできるだけ早く冷蔵庫や冷凍庫にしまいましょう。
冷蔵庫は満杯に詰め込むのではなく、約7割の容量を目安にして冷気が全体に行き渡るように管理してください。特に夏場は室温も高いため、お弁当や作り置き料理は保冷剤や保冷バッグを使って涼しい場所で保存するのが安全です。残った料理は早めに食べきるか、再加熱してから保存すると安心です。
「とりあえず冷蔵庫に入れたから大丈夫」という油断が、食中毒を招くこともあるので注意が必要です。
4. 「やっつける」確実に菌を殺す加熱と衛生管理
 食中毒を防ぐ最も確実な方法は、しっかりと加熱することです。多くの細菌は75度で1分以上加熱すれば死滅すると言われています。鶏肉やひき肉、魚介類などは特に中心まで十分に火を通すことが必要です。
食中毒を防ぐ最も確実な方法は、しっかりと加熱することです。多くの細菌は75度で1分以上加熱すれば死滅すると言われています。鶏肉やひき肉、魚介類などは特に中心まで十分に火を通すことが必要です。
調理の際には、見た目だけで加熱完了と判断せず、加熱ムラに注意しましょう。電子レンジ調理の場合は加熱ムラができやすいので、途中でかき混ぜたり、中心温度を確認したりすることをおすすめします。
包丁やまな板、ふきん、スポンジなどの調理器具は雑菌が繁殖しやすい場所です。熱湯消毒や漂白剤による殺菌を定期的に行い、使用後はすぐ洗って湿ったままにしないよう心掛けましょう。
また、冷凍食品は自然解凍せず、表示の指示通りに加熱してから食べることも重要です。安全のためには「中心まで火が通っているか」を基準に調理を行ってください。
5. 食中毒のサインと適切な受診タイミング
もし急な下痢、腹痛、嘔吐、発熱といった症状が現れた場合、食中毒の可能性を疑いましょう。
特に家族や同僚など複数の人が同じような症状を示している場合や、食後数時間から1日以内に症状が出た場合は食中毒の可能性が高いです。
軽度の場合は水分補給をしながら安静にすることが多いですが、高熱や血便、強い脱水症状がある場合は速やかに医療機関を受診してください。市販の下痢止め薬を安易に使うと、体内に毒素が溜まって症状が悪化する恐れがあります。
高齢者や乳幼児、基礎疾患のある方は重症化しやすいので、少しでも体調に異変を感じたら早めに相談することが大切です。自己判断を避け、適切な治療を受けることが回復への近道となります。
まとめ
\5つの基本を守り、安全な食生活を続けよう/
食中毒は、日々のちょっとした気遣いと正しい知識で十分に防げる病気です。
菌を「つけない・増やさない・やっつける」ことを軸に、食品の保存方法や加熱、調理器具の衛生管理をしっかり行いましょう。
そして体調に変化があれば早めに受診することが大切です。家族みんなで安全な食生活を守り、健康を保ちましょう。
監修医師 大柄 貴寛
国立弘前大学医学部 卒業。青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、日本屈指の高度な専門施設、クリニックで消化器内視鏡・外科手術治療を習得後、2020年10月大田大森胃腸肛門内視鏡クリニック開院、2024年12月東京新宿胃腸肛門内視鏡・鼠径ヘルニア日帰り手術RENA CLINIC開院。