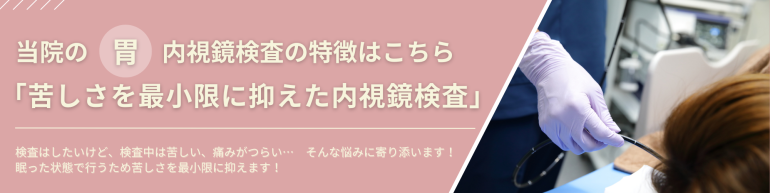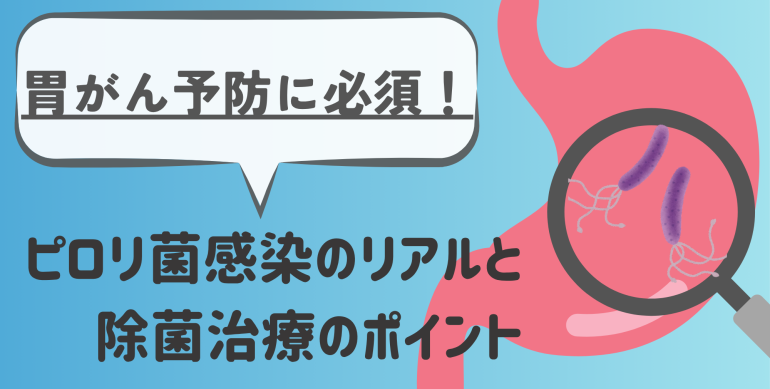
「ピロリ菌」という言葉は耳にしたことがあるものの、実際にどんな菌なのか詳しく知らない方も多いでしょう。
この菌は胃の粘膜に住み着き、長期間感染が続くと慢性胃炎や胃・十二指腸潰瘍、さらには胃がんの原因となることが知られています。
実は、日本人の約半数以上が感染しているとも言われ、気づかないうちに胃の健康が蝕まれているケースが非常に多いのです。
今回は、ピロリ菌感染の基本的な知識から感染経路、症状、検査方法、最新の除菌治療の流れまで、わかりやすく詳しくご紹介します。
大田大森胃腸肛門内視鏡クリニックでも行っている検査と治療体制についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
1. ピロリ菌感染って何?
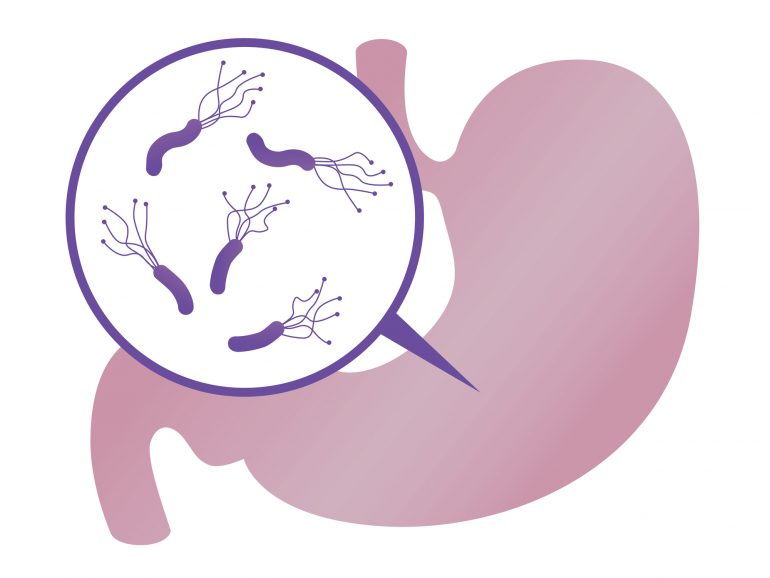 ピロリ菌は、胃の粘膜に棲みつくらせん状の細菌です。
ピロリ菌は、胃の粘膜に棲みつくらせん状の細菌です。
この菌が胃の粘膜に長くとどまることで、慢性的な炎症である慢性胃炎を引き起こします。
また、胃や十二指腸の粘膜が傷つき潰瘍ができることも多く、さらに放置すると胃がんのリスクも高まることが明らかになっています。
実際に胃がん患者の約99%が過去にピロリ菌に感染していたというデータもあります。
感染は多くの場合自覚症状がないため、胃カメラ検査や呼気テスト、血液検査などで初めて発見されることが多いです。
2. 感染経路・原因とリスク要因
 ピロリ菌は主に家族内感染が多く、親から子への口移しや食器の共有が感染経路として考えられています。
ピロリ菌は主に家族内感染が多く、親から子への口移しや食器の共有が感染経路として考えられています。
また、喫煙や過度の飲酒、ロキソニンなどのNSAIDsの常用、衛生環境の悪さも感染定着や胃粘膜の炎症を悪化させる要因です。
感染率は年齢とともに増加し、日本では60歳以上の約80%が感染しているという報告もあります。
3. 症状・検査・除菌の流れ
ピロリ菌感染だけで症状が出ることは稀ですが、以下のような胃の不調があれば注意が必要です。
-
・みぞおちの痛みや胃もたれ、胸やけ、吐き気
-
・食欲不振、体重減少、貧血、黒色便など
検査方法は胃カメラでの粘膜採取、簡便な尿素呼気試験、便中抗原検査や血液抗体検査などがあります。
陽性が確認されると、約7日間の除菌薬の服用が開始され、2か月後に効果判定を行います。一次除菌で失敗した場合は二次除菌に進み、合計で90%以上の高い成功率を誇ります。
大田大森胃腸肛門内視鏡クリニックでは、検査から除菌、判定、フォローアップまで一貫してサポートしています。
4. 放置するとどうなる?見逃せない危険サイン
ピロリ菌感染を放置すると、以下のような合併症リスクが高まります。
-
萎縮性胃炎:胃粘膜が薄くなり胃もたれや胸やけ、食欲不振が現れます。
-
胃潰瘍・十二指腸潰瘍:みぞおちの痛みや消化不良、時に出血や穿孔のリスクも。
-
胃がん:感染者の約1~3%に発症リスクがあり、粘膜萎縮から腸上皮化生、がんへと進行します。
-
その他免疫関連疾患:血小板減少性紫斑病などが報告されています。
これらは黒色便、激しい腹痛、急激な体重減少、嘔吐などの症状が現れやすく、気づいたらすぐに医療機関を受診することが重要です。
5. 感染予防と再感染チェック方法
 完全な予防は難しいものの、以下の対策で感染リスクを下げることができます。
完全な予防は難しいものの、以下の対策で感染リスクを下げることができます。
-
☑ 手洗いを徹底し、食器や箸の共有を避ける。
-
☑ 清潔な水や加熱処理された食品を心がける。
-
☑ 家族に感染疑いがあれば検査を検討し、口移しなどを控える。
-
☑ 除菌後も胃カメラで1~2年に一度は経過観察を。
-
☑ 喫煙や過度飲酒、NSAIDsの多用を控え、バランスの良い食事や適度な運動、ストレス管理を行う。
これらを継続することで、再感染や病変の進行を防ぎ、健康な胃を維持できます。
まとめ
ピロリ菌感染は自覚症状が出にくいため、知らずに進行しがちですが、慢性胃炎や潰瘍、胃がんと密接に関係しています。
検査で感染を確認し、早めの除菌治療が将来的なリスクを大幅に減らします。
衛生習慣や生活習慣の改善も感染予防に効果的です。
胃の違和感を感じたら、ぜひ早めの検査をおすすめします!
監修医師 大柄 貴寛
国立弘前大学医学部 卒業。青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、日本屈指の高度な専門施設、クリニックで消化器内視鏡・外科手術治療を習得後、2020年10月大田大森胃腸肛門内視鏡クリニック開院、2024年12月東京新宿胃腸肛門内視鏡・鼠径ヘルニア日帰り手術RENA CLINIC開院。