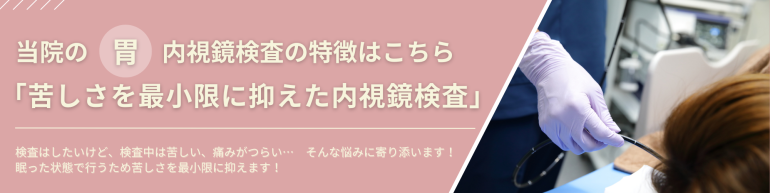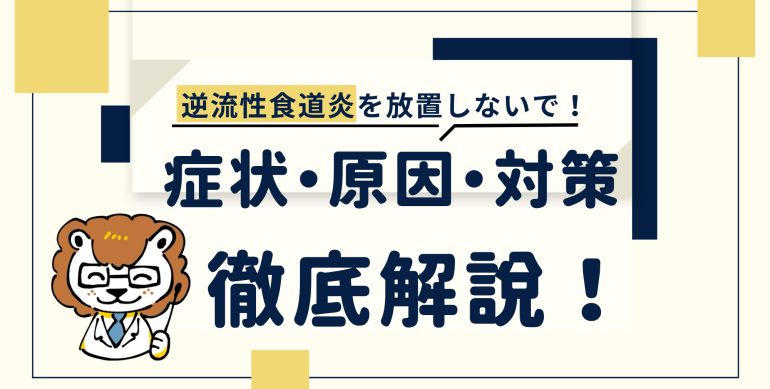
「最近、食後に胸がムカムカする」「喉に何かがつかえているような感覚が続く」
そんな症状を感じたことはありませんか?もしかすると、それは“逆流性食道炎”のサインかもしれません。軽く考えて放置してしまいがちですが、逆流性食道炎は放っておくと慢性化し、食道に深刻なダメージを与えることもある注意すべき疾患です。
このブログでは、逆流性食道炎のメカニズムから原因、日常生活でできるセルフケア、そして医療機関での検査・治療までを5つの視点からわかりやすく解説します。大田大森胃腸肛門内視鏡クリニックが推奨する、実践しやすい予防法もあわせてご紹介します。
1. 逆流性食道炎とは?|その仕組みとよくある症状
逆流性食道炎とは、胃酸や胃の内容物が食道へ逆流し、粘膜に炎症を引き起こす病気です。健康な状態では、胃と食道の間にある「下部食道括約筋」が逆流を防いでいますが、この筋肉がゆるむことで胃酸が逆流し、不快な症状が出るようになります。
主な症状は以下の通り:
-
・胸やけ(みぞおちから喉にかけての焼けるような感覚)
-
・酸っぱい液が喉まで上がってくる「呑酸」
-
・喉の違和感、声のかすれ、乾いた咳
-
・食後や横になった時に起こる胸の痛み
初期は風邪や胃もたれと勘違いされがちですが、長期間放置すると「バレット食道」というがん化リスクのある状態に進行することも。早期に気づき、対処することがとても大切です。
2. なぜ起きる?逆流性食道炎の原因と生活習慣の関係
 逆流性食道炎は、以下のような生活習慣や体質が原因で引き起こされます。
逆流性食道炎は、以下のような生活習慣や体質が原因で引き起こされます。
-
・食べ過ぎ・早食い:胃が圧迫され、逆流しやすくなります。
-
・脂っこいもの・刺激物の摂取:カフェインやアルコールは括約筋を緩めてしまいます。
-
・喫煙:ニコチンが胃酸の分泌を促し、逆流を悪化させます。
-
・加齢や肥満:筋力の低下や内臓脂肪の増加で胃酸が上がりやすくなります。
日々の生活習慣が症状の発生に深く関わっています。「ちょっとした胸やけ」で済ませず、生活を見直すことが改善への第一歩です。
3. 自宅でできる!逆流性食道炎をやわらげるセルフケア
 症状が軽度の場合、生活習慣の改善で症状の緩和が期待できます。
症状が軽度の場合、生活習慣の改善で症状の緩和が期待できます。
食事の工夫:
-
・腹八分目を意識して食べすぎを防ぐ
-
・油っこいものや香辛料など刺激の強い食べ物は控える
-
・よく噛んでゆっくり食べることで胃への負担を減らす
生活習慣のポイント:
-
・食後すぐ横にならない(30分以上は座って過ごす)
-
・枕を高くして寝る(逆流を防ぐ効果あり)
-
・締め付けの強い服装や姿勢の悪さも見直す
-
・軽い運動や入浴でストレスを緩和
市販薬を使う前に、まずはこれらのケアを試してみてください。セルフケアで改善しない場合は医師の診察が必要です。
4. 医療機関での検査と治療法
 症状が長引いたり、強くなった場合は医療機関での検査と治療が大切です。
症状が長引いたり、強くなった場合は医療機関での検査と治療が大切です。
主な検査:
-
・内視鏡検査(胃カメラ):粘膜の炎症やバレット食道の有無を確認
-
・pHモニタリング:食道内の酸度を測定し逆流の頻度を把握
-
・バリウム検査:消化管の形状を観察
治療法:
-
・PPI(プロトンポンプ阻害薬):胃酸の分泌を強力に抑える
-
・H2ブロッカー:軽症の場合に使用
-
・消化管運動改善薬:胃の動きを助け、胃の内容物をスムーズに排出
症状と生活スタイルに応じて薬の種類を調整しながら、再発を防ぐことがポイントです。
5. 再発させないために|日常生活でできる予防策
 逆流性食道炎は再発しやすいため、以下の点を継続的に意識しましょう。
逆流性食道炎は再発しやすいため、以下の点を継続的に意識しましょう。
-
・夕食は就寝3時間前までに済ませる
-
・就寝時は頭を15〜20cmほど高くして寝る
-
・肥満予防・体重管理で腹圧を下げる
-
・締め付けの強い衣類を避け、姿勢を正す
-
・禁煙・節酒・ストレスケアも非常に重要です
定期的な胃カメラ検査や診察を受けることで、症状の変化を早期に把握し、重症化を防ぐことができます。
✅ まとめ
逆流性食道炎は軽く見られがちですが、症状を放置すると慢性化し、生活の質を大きく下げる原因になります。
正しい知識と対策を身につけ、早期からケアを始めることで、快適な毎日を取り戻すことができます。
気になる症状がある場合は、ぜひ大田大森胃腸肛門内視鏡クリニックにご相談ください。
監修医師 大柄 貴寛
国立弘前大学医学部 卒業。青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、日本屈指の高度な専門施設、クリニックで消化器内視鏡・外科手術治療を習得後、2020年10月大田大森胃腸肛門内視鏡クリニック開院、2024年12月東京新宿胃腸肛門内視鏡・鼠径ヘルニア日帰り手術RENA CLINIC開院。