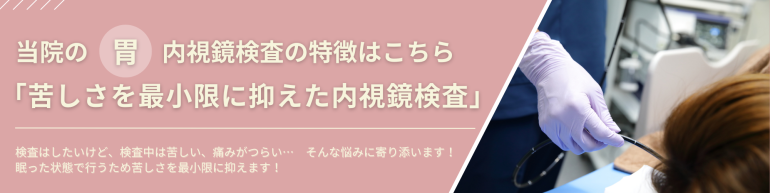「バレット食道」という名前を聞いたことはあっても、「普通の逆流性食道炎とどう違うの?」と疑問に思う方は少なくありません。
実はどちらも胃酸の逆流が原因ですが、その進行過程や体への影響、将来的なリスクは大きく異なります。
バレット食道は、長期的に胃酸や胆汁の逆流によって食道の粘膜が変化し、本来の構造が「胃仕様」に置き換わってしまう状態です。この粘膜変化は、食道がん(特に食道腺がん)の発症リスクを高める重要なサインでもあります。今回は、①バレット食道とは何か②逆流性食道炎との違い③診断・治療・予防のポイントを詳しく解説します。
1. バレット食道とは?粘膜変化のメカニズム
健康な食道は「扁平上皮」という構造で覆われていますが、胃酸や胆汁の逆流が続くと炎症と修復が繰り返され、その過程で粘膜が「円柱上皮」という胃に似た構造に変わります。
この状態をバレット食道と呼びます。バレット食道には2つのタイプがあります。
-
①SSBE(ショートセグメント):変化の範囲が3cm未満(日本人の約99%)
-
②LSBE(ロングセグメント):変化の範囲が3cm以上
変化が広いLSBEでは、食道腺がんのリスクが高まり、年率で約0.3〜1.2%ががん化するという報告もあります。
近年、欧米型の食生活や肥満の増加により、逆流性食道炎やバレット食道の患者数は日本でも増加傾向です。
2. 逆流性食道炎との違いと症状の特徴
 逆流性食道炎は、胃酸が食道へ逆流して粘膜に炎症やびらんが生じる状態です。主な症状は以下の通りです。
逆流性食道炎は、胃酸が食道へ逆流して粘膜に炎症やびらんが生じる状態です。主な症状は以下の通りです。
-
・胸焼け
-
・呑酸(酸が上がる感じ)
-
・げっぷ
-
・胸痛
-
・喉の違和感
一方でバレット食道は、逆流性食道炎が長期間続いた結果、粘膜が円柱上皮に置き換わった状態を指します。特徴的なのは、症状がほとんどないこと。胸焼けなどがあっても、それは逆流性食道炎による症状である場合が多いです。そのため、無症状のまま進行し、がんリスクが高まることも珍しくありません。
【違いのまとめ】
-
逆流性食道炎:炎症・びらん/症状あり/治療で改善可能
-
バレット食道:粘膜構造が変化/無症状が多い/定期観察必須/がん化リスクあり
3. 診断・治療・フォローアップの流れ
診断には**胃カメラ(内視鏡検査)**が必須です。粘膜の色調や質感を観察し、必要に応じて組織を採取(生検)します。
治療の柱は3つ!
-
①**胃酸抑制薬(PPIなど)**で逆流を防ぐ
-
②生活習慣の改善:肥満解消・禁煙・刺激物制限・就寝前の飲食を避ける
-
③定期的な胃カメラ:おおむね年1回の経過観察
粘膜そのものを元の状態に戻す治療法は確立されていないため、逆流のコントロールと早期発見が重要です。
4. 生活習慣でできる予防とセルフケア
日常生活でできる予防法は次の通りです。
 【食生活の工夫】
【食生活の工夫】
-
・脂っこい食事・香辛料・カフェイン・アルコールを控える
-
・よく噛んでゆっくり食べ、腹八分目でストップ
-
・食後2〜3時間は横にならない
【姿勢と生活リズム】
-
・肥満や便秘による腹圧上昇を避ける
-
・猫背を防ぎ、背筋を伸ばす姿勢を意識
【禁煙とストレス対策】
-
・喫煙は逆流を助長するため禁煙推奨
-
・睡眠不足や過度なストレスは胃酸分泌を増加させるため、十分な休養を取る
まとめ
\ 早期発見が命を守る /
バレット食道は、逆流性食道炎が長期化して食道の粘膜が胃仕様に変わった状態で、特にLSBEは食道腺がんリスクが高くなります。
診断には胃カメラが不可欠で、定期的な観察と生活改善が重要です。
大田大森胃腸肛門内視鏡クリニックでは、最新機器と専門医による内視鏡検査から生活指導、長期フォローまでを包括的に行っています。
胸焼けや呑酸などの症状がある方、健康診断で異常を指摘された方は、早めの受診をおすすめします。
監修医師 大柄 貴寛
国立弘前大学医学部 卒業。青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、日本屈指の高度な専門施設、クリニックで消化器内視鏡・外科手術治療を習得後、2020年10月大田大森胃腸肛門内視鏡クリニック開院、2024年12月東京新宿胃腸肛門内視鏡・鼠径ヘルニア日帰り手術RENA CLINIC開院。