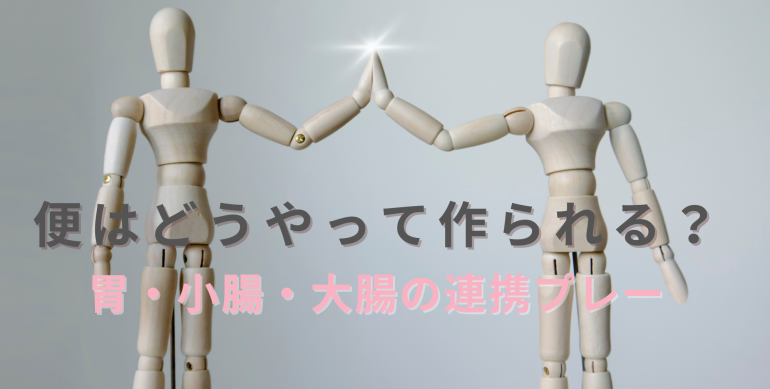
「便って、ただ食べたものの残りカスが出てくるだけでしょ?」
そう思っていませんか?実は、私たちが毎日当たり前のように排出している便は、胃・小腸・大腸・神経・筋肉が連携しながら、何十時間もかけて作られています。
食べ物が口に入ってから便になるまでには24〜72時間かかることもあり、その間に栄養の吸収、水分の調整、腸内細菌との共同作業など、見えないドラマが繰り広げられています。
今回は、便ができるまでの流れと健康チェックのポイント、そして毎日の快便を目指すための生活習慣まで、わかりやすく解説します。
1. 口から大腸まで!便ができるまでの道のり
-
 【口・胃での準備】
【口・胃での準備】-
・ 食べ物は噛み砕かれ、唾液で湿らされて胃へ
-
⇒ 胃酸や消化酵素で粥状になり、小腸へ送られます
-
-
【小腸での吸収(約7時間)】
-
・ 栄養と水分の大半(約7L分)を吸収
-
⇒ 残った食物繊維や不要成分が大腸へ移動
-
-
【大腸での仕上げ】
-
・ 水分と電解質をさらに吸収
-
⇒ 腸内細菌が食物繊維などを分解し、一部は短鎖脂肪酸となって腸のエネルギー源に
-
⇒ 上行結腸で液体状 → 横行結腸で半固形 → 下行結腸で固形化
-
⇒ 最後に直腸へ送られ、便として貯留
-
この過程で、最初は約9Lの液体だった内容物が、最終的には100〜200gの便になります。
2. 大腸での水分吸収と便の硬さの関係
-
 ・大腸での通過時間が長い → 水分が吸収されすぎて硬くなり便秘気味に
・大腸での通過時間が長い → 水分が吸収されすぎて硬くなり便秘気味に -
・通過時間が短い → 水分が多く残り、下痢状に
水分量・食物繊維の摂取量・腸の動き・ストレスなど、さまざまな要因が便の形状に影響します。
便の性状は腸内環境のバロメーター。普段から観察する習慣をつけることが大切です。
3. 排便のしくみと体の連携プレー
便が直腸に到達すると、脳へ「便意」の信号が送られます(排便反射)。
特に朝食後や起床時に活発になるのは、胃や小腸が動く刺激で大腸も動くからです。
排便には以下の連携が不可欠です。
-
・ぜん動運動:大腸の筋肉が便を押し出す
-
・腹筋・横隔膜の力:ふんばりをサポート
-
・内・外肛門括約筋の調節:便を出すタイミングをコントロール
-
・正しい姿勢:前かがみで骨盤底筋が緩み、スムーズに排出
この連携が崩れると便秘や便失禁の原因になります。
4. 正常な便を見分ける「ブリストルスケール」
 ブリストルスケールは、便を7タイプに分類する指標です。
ブリストルスケールは、便を7タイプに分類する指標です。
-
・タイプ3〜4:理想(ソーセージ状でひび割れ or 滑らか)
-
・タイプ1〜2:硬い(便秘や水分不足のサイン)
-
・タイプ5〜7:柔らかい(下痢や腸の動きすぎ)
色(茶〜黄土色)、におい、排便回数(1日1回〜週3回)も健康チェックの目安になります。
5. 健康な便をつくる生活習慣
-
 ・水分をしっかり摂る(1.5〜2L/日)
・水分をしっかり摂る(1.5〜2L/日) -
・食物繊維を適量摂取(野菜・海藻・きのこ・豆類)
-
・発酵食品で腸内環境を整える(ヨーグルト・納豆・キムチ)
-
・規則正しい生活(朝食後の排便習慣づくり)
-
・適度な運動(ウォーキング・腹筋運動)
まとめ
便ができるまでには、胃・小腸・大腸・神経・筋肉の複雑な連携が関わっています。
便の形や硬さは、腸の健康状態を映す大切なサイン。日々の食事・水分・運動・排便習慣を見直すことで、健康な便を維持できます。
大田大森胃腸肛門内視鏡クリニックでは、排便や腸の健康に関する診察・生活指導を行っています。便や腸内環境に不安がある方は、お気軽にご相談ください。
監修医師 大柄 貴寛
国立弘前大学医学部 卒業。青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、日本屈指の高度な専門施設、クリニックで消化器内視鏡・外科手術治療を習得後、2020年10月大田大森胃腸肛門内視鏡クリニック開院、2024年12月東京新宿胃腸肛門内視鏡・鼠径ヘルニア日帰り手術RENA CLINIC開院。




















