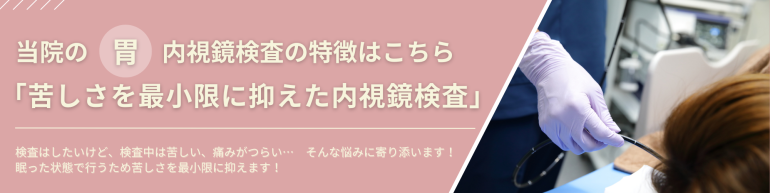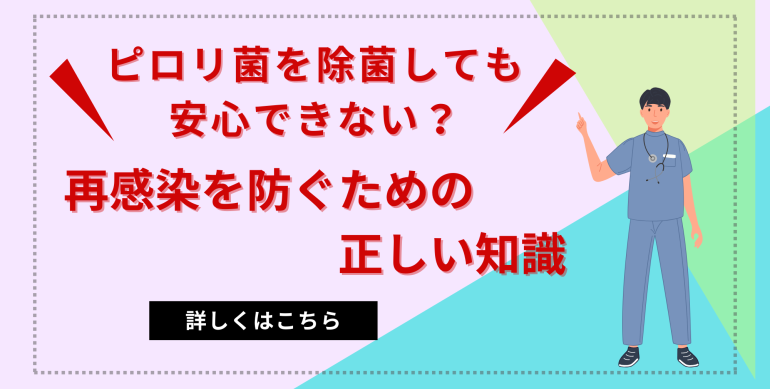
「ピロリ菌を除菌したから、もう一生大丈夫」と思っていませんか?実はそこに大きな落とし穴があります。
ピロリ菌には、再感染や再燃といったリスクが存在し、知らないうちに胃炎が進行してしまうケースもあるのです。
特にピロリ菌は胃がんの大きな要因としても知られているため、除菌後も油断は禁物です。
本記事では、ピロリ菌再感染の原因やリスク、予防法、検査のタイミングまで、大田大森胃腸肛門内視鏡クリニックが詳しく解説します。
1. ピロリ菌とは?なぜ除菌で終わりじゃないのか
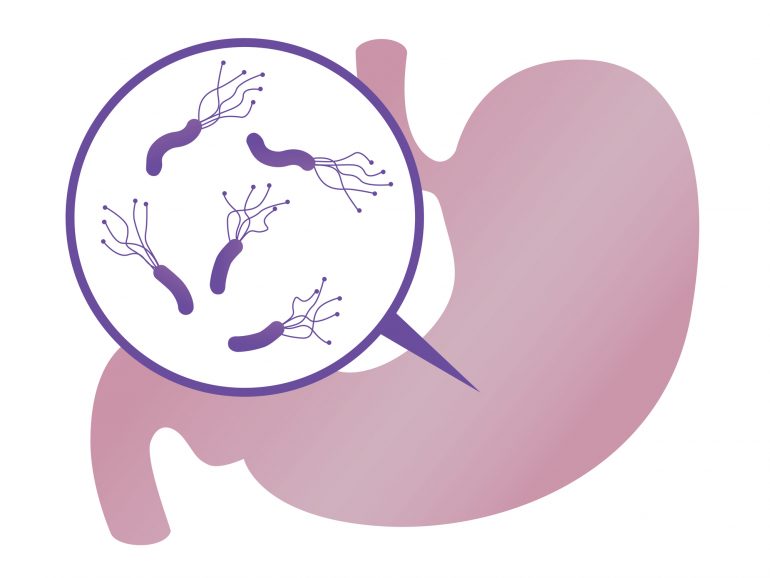 ピロリ菌(Helicobacter pylori)は胃の粘膜に住みつく細菌で、胃炎・胃潰瘍・十二指腸潰瘍、さらには胃がんの原因にもなることがわかっています。
ピロリ菌(Helicobacter pylori)は胃の粘膜に住みつく細菌で、胃炎・胃潰瘍・十二指腸潰瘍、さらには胃がんの原因にもなることがわかっています。
多くの人は幼少期に感染し、そのまま成人期まで持ち続けるケースが多いのですが、近年では「除菌治療」が広がり、感染率は減少しています。
治療は、抗生物質2種類+胃酸を抑える薬を1週間服用する方法が一般的で、成功率は80〜90%と高めです。
しかし、問題はその後です。
-
・再感染:一度菌を除去しても、再び新しいピロリ菌に感染するケース
-
・再燃:除菌できたと思ったものの、わずかに残っていた菌が再び増殖するケース
このように「完全に終わり」ではなく、再びリスクが潜んでいるのです。
2. 再感染と再燃の違いを理解しよう
似ているようで異なる再感染と再燃。それぞれの特徴を知っておきましょう。
-
再感染:外部から新しく菌が入り込むケース。
↳ 家族間での食器共有、親が子どもへ口移しで食べ物を与える、井戸水などが原因になることがあります。 -
再燃:実は菌が完全に取り切れていなかったケース。
↳ 抗生物質に耐性を持った菌が残っていたり、薬を正しく服用できなかった場合に起こります。
再感染率は年間で約1〜3%と多くはありませんが、衛生環境や生活習慣によってはリスクが高まります。さらに怖いのは、再感染しても初期はほとんど症状がないこと。
胃もたれや食欲不振を「ただの疲れ」と見過ごしてしまうことも多いのです。
3. 再感染を防ぐ生活習慣のポイント
ピロリ菌再感染を防ぐためには、日々の生活習慣がとても重要です。
(1) 衛生習慣
-
 ・食器・箸を家族で使い回さない
・食器・箸を家族で使い回さない -
・子どもに口移しで食べ物を与えない
-
・手洗い・うがいをこまめに
-
・歯ブラシは定期的に交換する
(2) 食生活
-
・胃を荒らすアルコール・辛い食べ物・塩分過多は控えめに
-
・抗酸化作用のあるビタミンA・C・Eを含む食材を意識して摂取
-
・ヨーグルト・味噌などの発酵食品で腸内環境を整える
(3) ストレス対策
-
・睡眠不足や過労を避ける
-
・リラックスする時間を確保する
-
・ストレスは胃酸分泌を増加させ、胃粘膜を弱めるため注意が必要
「除菌で終わり」ではなく、「除菌からがスタート」という意識を持つことが、再感染予防の第一歩です。
4. 検査のタイミングと再感染時の対応
除菌治療が終わったら、すぐに安心してはいけません。
-
・除菌確認検査:治療終了後1〜2か月後に実施(呼気試験や便中抗原検査)
-
・1年後の再検査:長期的に陰性が続いているかをチェック
再感染が疑われるサインは、慢性的な胃もたれ・食欲不振・吐き気、または胃カメラで胃炎の再発が見られる場合です。
再感染が確認された場合は、再度の除菌治療を行います。2回目以降の治療では、耐性菌の有無を考慮して薬の組み合わせを変更することもあります。
5. 大田大森胃腸肛門内視鏡クリニックでできること
大田大森胃腸肛門内視鏡クリニックでは、
-
・除菌後の定期的なフォローアップ検査
-
・再感染時の治療計画
-
・衛生習慣や生活習慣のアドバイス
を通じて、患者さんの胃の健康を長期的にサポートしています。
「胃が重い」「また不調が出てきた」そんなときは自己判断せず、医師に相談することが何より大切です。
監修医師 大柄 貴寛
国立弘前大学医学部 卒業。青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、日本屈指の高度な専門施設、クリニックで消化器内視鏡・外科手術治療を習得後、2020年10月大田大森胃腸肛門内視鏡クリニック開院、2024年12月東京新宿胃腸肛門内視鏡・鼠径ヘルニア日帰り手術RENA CLINIC開院。