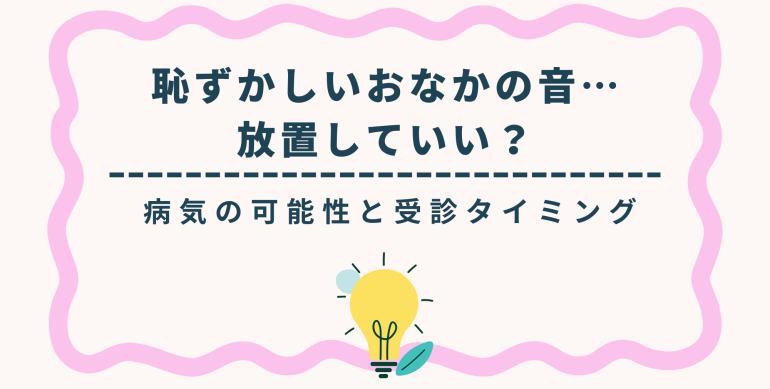
「会議中におなかが大音量で鳴ってしまった」「食後すぐにゴロゴロが止まらない」——誰もが一度は経験したことがあるはずです。
多くの場合は腸がしっかり働いている証拠ですが、ときには消化不良や過敏性腸症候群(IBS)などの病気が関係している場合もあります。
この記事では、おなかの音が鳴る仕組みや原因、日常でできる対策、そして医療機関を受診したほうがよいサインについて、わかりやすく解説します。
1. おなかの音ってどうして鳴るの?
おなかの音(腸蠕動音)は、腸が消化のために収縮・弛緩を繰り返すときに、ガスや消化液が移動して響く音です。
-
・食後:胃や腸が消化を始めることで音が強くなる
-
・空腹時:食べ物を探す「空腹収縮」により音が鳴る
つまり、音がすること自体は自然な現象であり、腸が正常に働いているサインといえます。
ただし「音が普段より大きい」「頻繁に鳴る」といった変化には注意が必要です。
2. 音が大きくなる原因とは?
 おなかの音がいつも以上に大きくなる要因はいくつかあります。
おなかの音がいつも以上に大きくなる要因はいくつかあります。
-
消化不良・食べ過ぎ・早食い
↳脂っこい食事や炭水化物の過剰摂取、よく噛まずに食べることで腸がフル稼働し、音が強まります。 -
ガスの増加
↳豆類・炭酸飲料・野菜などガスを発生しやすい食品の摂取や、空気の飲み込み癖によって音が響きやすくなります。 -
ストレスや過敏性腸症候群(IBS)
↳心の緊張が腸に伝わり、腸の動きが不規則に。下痢や腹痛を伴い、音も大きく頻繁になるケースがあります。 -
腸の炎症や感染症
↳胃腸炎などの場合、蠕動音が強く出ると同時に、下痢・発熱・腹痛などの症状を伴うことが多いです。
3. 日常でできる対策:音を減らす生活改善
 おなかのゴロゴロ音を和らげるために、次のような工夫が役立ちます。
おなかのゴロゴロ音を和らげるために、次のような工夫が役立ちます。
-
「食生活の改善」
消化に優しい食事(おかゆ、野菜スープ、豆腐など)を取り入れ、よく噛んでゆっくり食べる習慣をつけましょう。 -
「ガスを溜めない工夫」
炭酸飲料やガスを発生しやすい食品を控え、食後すぐに横にならないよう注意します。軽いストレッチや散歩も効果的です。 -
「ストレスケア」
深呼吸や趣味、十分な睡眠をとり、自律神経を整えることが腸のリズム安定につながります。 -
「生活リズムの安定」
毎日同じ時間に食事と排便を行い、腸のリズムを整えることも大切です。
4. こんなときは要注意!受診を考えるタイミング
おなかの音は多くの場合心配いりませんが、以下のような症状がある場合は医師の診察を受けましょう。
-
・音に加えて強い腹痛や下痢が続く
-
・体重減少・血便・発熱がある
-
・長期間続く便秘や下痢を繰り返す
-
・40代以降で腸の調子が安定しない
これらはIBSや消化器系疾患の可能性があり、早めの受診が安心につながります。
まとめと当院からのメッセージ
おなかの音は「腸が働いている証拠」であり、多くは自然な現象です。
しかし、音が大きすぎたり頻繁すぎたりすると、生活に支障をきたしたり病気のサインであることも。食生活やストレスケアで改善を目指し、それでも続く場合は早めの受診がおすすめです。
大田大森胃腸肛門内視鏡クリニックでは、消化器内科の専門医が腸に関する不安や症状に丁寧に対応しています。気になる方はぜひご相談ください。
監修医師 大柄 貴寛
国立弘前大学医学部 卒業。青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、日本屈指の高度な専門施設、クリニックで消化器内視鏡・外科手術治療を習得後、2020年10月大田大森胃腸肛門内視鏡クリニック開院、2024年12月東京新宿胃腸肛門内視鏡・鼠径ヘルニア日帰り手術RENA CLINIC開院。



















