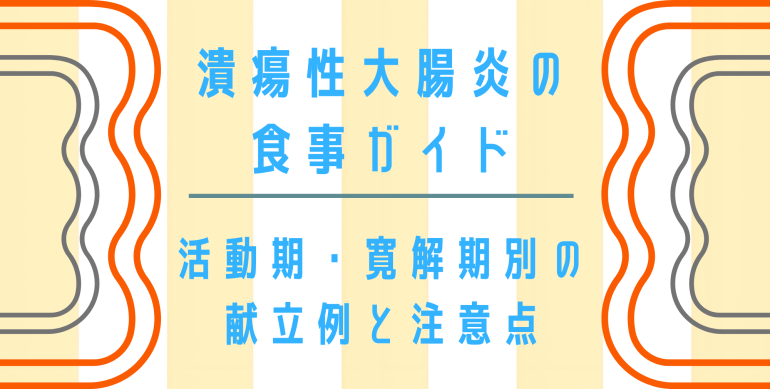
「何を食べたらいいのか分からない…」「食事が怖い…」潰瘍性大腸炎(UC)を抱える方からよく聞かれるお悩みです。腸に炎症があるこの病気では、食べ物が直接症状に影響することが少なくありません。そのため、食事は薬の治療と同じくらい大切な自己管理の一つです。
しかし、ネットやSNSには膨大な情報があり、「これは本当に正しいの?」と迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
この記事では、医療的な視点から潰瘍性大腸炎と食事の基本をわかりやすく解説し、毎日の食生活に役立つ知識をまとめました。
1. 潰瘍性大腸炎における食事の役割
食事療法は潰瘍性大腸炎を直接「治す」わけではありませんが、症状を安定させるうえで非常に重要です。腸に炎症がある時期には、ちょっとした食事内容の違いが腹痛や下痢、血便などの症状を悪化させることがあります。
特に活動期には腸の粘膜が敏感になっているため、脂っこいもの・繊維の多い食材・刺激物などは避ける必要があります。一方で、寛解期には腸を労わりつつ栄養バランスを整え、体力や免疫力を保つことが大切です。
つまり、食事は「病気と共に暮らすための土台」。自分の体と向き合いながら、無理のない範囲で工夫していくことが必要です。
2. 活動期と寛解期で異なる食事の考え方
潰瘍性大腸炎は、「症状が出る活動期」と「落ち着く寛解期」が繰り返されるのが特徴です。このサイクルに合わせて食事内容を調整することが基本となります。
【活動期】
 腸の炎症が強い状態で、腹痛や下痢が起こりやすい時期です。
腸の炎症が強い状態で、腹痛や下痢が起こりやすい時期です。
-
ポイント:「低脂肪」「低残渣(繊維が少ない)」「消化が良い」食品を選ぶ
-
例:白粥、うどん、そうめん、豆腐、卵、白身魚、やわらかく煮た野菜、すりおろしリンゴ
【寛解期】
症状が落ち着いている時期。少しずつ食事を広げることが可能です。
-
ポイント:栄養バランスを重視し、再燃を予防
-
例:鶏むね肉、鮭、納豆、玄米や雑穀米(少量から)、ヨーグルトなど
活動期・寛解期のどちらでも共通するのは、自分に合う食材を見つけることです。食べたものと体調を日記に記録すると、自分の「安心できる食リスト」を作れます。
3. 食べてよいもの・避けたいもの
活動期におすすめの食材
-
 ・白粥、うどん、そうめん
・白粥、うどん、そうめん -
・絹ごし豆腐、卵、白身魚
-
・バナナ、すりおろしリンゴ
-
・にんじん・かぼちゃの煮物
-
・ポタージュスープ
避けたい食材
-
・揚げ物、脂の多い肉
-
・生野菜、硬い根菜、海藻類
-
・カレーやキムチなど香辛料が強い料理
-
・アルコール、カフェイン飲料
-
・牛乳やチーズ(合わない場合)
寛解期に取り入れやすいもの
-
・鶏肉、魚、大豆製品
-
・雑穀米や玄米(少しずつ)
-
・発酵食品(納豆、ヨーグルトなど)
「絶対にNG」という食材はなく、個人差が大きいのが潰瘍性大腸炎の特徴です。少量から試し、自分の体に合うかどうかを確認しましょう。
4. 食事に関するよくある質問と誤解
 Q. 絶食が一番良い?
Q. 絶食が一番良い?
→ A.一部の重症例で一時的に必要な場合もありますが、基本は「食べながら治す」方針です。
Q. 牛乳や乳製品は全てNG?
→ A.個人差があります。ヨーグルトが合う方もいれば、牛乳で下痢が悪化する方もいます。
Q. サプリや栄養補助食品は?
→ A.栄養が不足しがちな場合には有効ですが、必ず医師と相談しましょう。
Q. 一生制限食?
→ A.寛解期には食事の幅を広げられます。無理のない楽しみ方を見つけましょう。
5. 続けやすい工夫とサポート体制
-
・完璧を目指さない:7割意識するだけでも十分効果あり
- ・レパートリーを広げる:蒸し料理やスープ、豆腐料理で工夫
-
・備えをしておく:低残渣食のレトルトや栄養補助食品を常備
大田大森胃腸肛門内視鏡クリニックでは、医師と管理栄養士が連携し、患者さんに合わせた食事指導を行っています。一人で悩まず、専門家のサポートを受けながら安心して食生活を続けることが大切です。
まとめ
潰瘍性大腸炎の食事管理は、症状を安定させるための大切な自己管理の一部です。
活動期と寛解期で食べ方を調整し、自分に合ったスタイルを見つけていくことが、長く病気と付き合うカギになります。
制限が多く感じても、工夫次第で無理なく続けられるはずです。
監修医師 大柄 貴寛
国立弘前大学医学部 卒業。青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、日本屈指の高度な専門施設、クリニックで消化器内視鏡・外科手術治療を習得後、2020年10月大田大森胃腸肛門内視鏡クリニック開院、2024年12月東京新宿胃腸肛門内視鏡・鼠径ヘルニア日帰り手術RENA CLINIC開院。




















