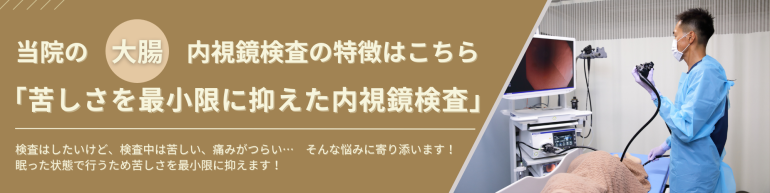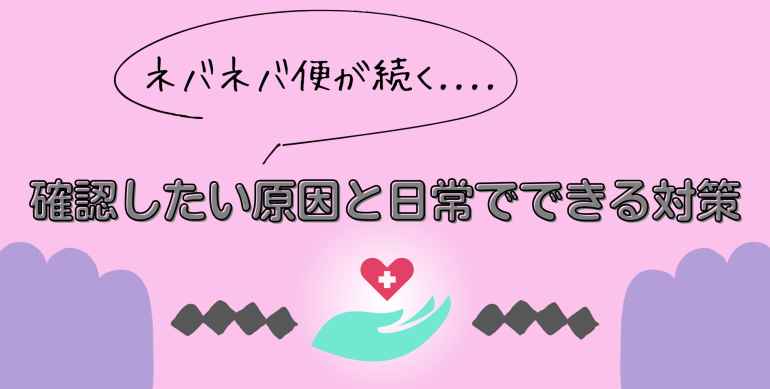
最近、トイレで「便がベタベタ、ネバネバしている」と感じたことはありませんか?拭いても落ちない、手やトイレットペーパーに付くような粘り気のある便は、誰にでも一度は経験があります。軽度の粘液便なら心配ないこともありますが、頻繁に起こる場合や血が混ざる場合は、腸内でトラブルが起きているサインかもしれません。
この記事では「粘りのある便」の特徴、原因、チェックポイント、日常でできる改善方法、受診すべきタイミングまで、消化器内科の視点からわかりやすく解説します。
早めに対処して、安心できる毎日を取り戻しましょう。
1. 粘りがある便とは?
粘り気のある便、いわゆる「粘液便」とは、便にゼリー状の粘液が付着している状態を指します。この粘液は腸の内側を保護するために分泌され、少量であれば正常です。しかし、ベタつきが強い・拭いても落ちない・頻繁に起こる場合は注意が必要です。
原因としては以下のようなことが考えられます:
-
・消化不良や一時的な腸の炎症
-
・ストレスや過敏性腸症候群(IBS)
-
・潰瘍性大腸炎、クローン病などの炎症性腸疾患
-
・大腸ポリープや大腸がん
特に腹痛や血便を伴う場合は、早めの医療機関受診をおすすめします。
2. 色や状態からわかる原因別チェック
 粘液の色や量によって、原因をある程度推測できます。
粘液の色や量によって、原因をある程度推測できます。
-
透明な粘液:軽い腸の不調やストレスによる場合が多い。腹痛がなければ数日様子を見てもよいことも。
-
白っぽい粘液:腸粘膜の傷や慢性的炎症の可能性。潰瘍性大腸炎の初期症状かもしれません。
-
黄色・緑の粘液:消化不良や腸内バランスの乱れ。腸内細菌や胆汁の影響も考えられます。
-
ピンク〜赤い粘液:直腸の病変や痔などでの出血の可能性。鮮血の場合は早めに確認を。
-
黒っぽい粘液や血混じり:大腸や小腸の深部での出血が疑われます。潰瘍性大腸炎、クローン病、大腸がんなどの可能性があり、早急な受診が必要です。
色や形だけで自己判断せず、継続する場合は医療機関で相談しましょう。
3. 日常でできる対策と生活改善
粘液便の改善には、日常生活の工夫が欠かせません。「腸にやさしい生活」を心がけましょう。
 「食生活の改善」
「食生活の改善」
-
・発酵食品(ヨーグルト・納豆・味噌)を取り入れる
-
・食物繊維(野菜・海藻・きのこ)をバランスよく摂取
-
・脂っこい食事・辛いもの・アルコールは控えめに
 「水分補給」
「水分補給」
-
・便の状態を整えるために1日1.5〜2リットルを目安に水分補給
「運動と睡眠の質向上」
-
・ウォーキングや軽いストレッチで腸の動きを活性化
-
・規則正しい生活と十分な睡眠で自律神経を整える
「便意を我慢しない習慣」
-
・朝食後など一定のタイミングで排便習慣をつけると腸リズムが整いやすい
4. 注意すべき兆候と専門受診の目安
以下の症状がある場合は早めに受診してください:
-
・粘液便が2週間以上続く
-
・血が混ざっている(赤・黒・茶色)
-
・腹痛、下痢、便秘が頻発
-
・発熱や体重減少がある
-
・家族に大腸疾患の既往歴がある
-
・40歳以上で大腸カメラ未受診
これらは潰瘍性大腸炎、クローン病、大腸がんなどの可能性があり、放置すると悪化します。大田大森胃腸肛門内視鏡クリニックでは、消化器内科専門医が原因の特定と適切な治療を行います。
5. まとめと当院からのメッセージ
粘りのある便は、腸からの重要なサインです。軽度の生活習慣の乱れが原因で改善することもありますが、長引く場合や血が混ざる場合は早期受診が必要です。
大田大森胃腸肛門内視鏡クリニックでは、粘液便を含む便の異常に対して、丁寧なカウンセリングと専門的な検査を行っています。気になる症状があれば、我慢せずご相談ください。
監修医師 大柄 貴寛
国立弘前大学医学部 卒業。青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、日本屈指の高度な専門施設、クリニックで消化器内視鏡・外科手術治療を習得後、2020年10月大田大森胃腸肛門内視鏡クリニック開院、2024年12月東京新宿胃腸肛門内視鏡・鼠径ヘルニア日帰り手術RENA CLINIC開院。