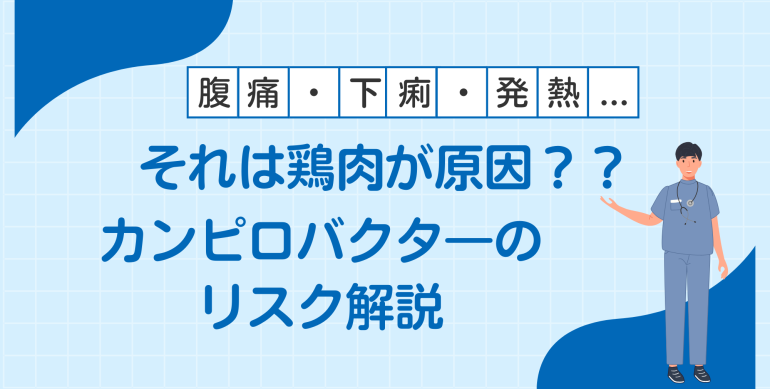
「昨日の焼き鳥、少しレアで美味しかったな…」そんな翌日からお腹の痛みや下痢、発熱に悩まされる。
これは、カンピロバクター食中毒の典型的なパターンです。特に夏場は発生件数が増えるため注意が必要です。
カンピロバクターは一見ありふれた菌ですが、強い腹痛や長引く下痢を引き起こすだけでなく、まれに神経疾患を合併することもあるため油断できません。
ここでは原因から症状、予防法まで詳しく解説します。
1. カンピロバクターってどんな菌?感染ルートを知ろう
カンピロバクターは、牛・豚・鶏などの腸管に存在する細菌で、日本では鶏肉が最も一般的な感染源です。
特に「生焼けの鶏肉」「鶏刺し」などが大きなリスク。
この菌は熱に弱く、中心部75℃以上で1分以上加熱すれば死滅します。しかし、表面だけをあぶった肉や、内部が赤いままの唐揚げなどでは菌が残ります。
さらに怖いのは、包丁・まな板・手指を介した二次汚染。鶏肉を切ったまな板でそのまま野菜を切ると、菌が移ってしまうのです。
しかも、わずか数百個の菌でも発症するため「ちょっとだから大丈夫」という油断が大きな落とし穴になります。
2. 主な症状と潜伏期間
 感染すると、腹痛・下痢・発熱・吐き気といった胃腸炎症状が現れます。
感染すると、腹痛・下痢・発熱・吐き気といった胃腸炎症状が現れます。
ただし、症状が出るまでには1〜7日の潜伏期間があるため、「食べたのは数日前だから違うだろう」と自己判断しがちです。
便は水様便で血が混じることもあり、腹痛は強烈な場合があります。発熱は微熱から38℃以上まで幅があり、体力を消耗することも少なくありません。
特に子どもや高齢者、免疫力が低下している人は重症化しやすく、脱水症状に注意が必要です。
さらにごくまれに、数週間後にギラン・バレー症候群という神経の病気を合併することが知られています。
3. 治療と受診の目安
多くは自然に回復しますが、症状が強い場合には受診が必要です。
-
基本は水分と安静:下痢や発熱で失われた水分・電解質を補うため、経口補水液をこまめに摂る。
-
点滴が必要な場合:嘔吐で水分が摂れない、尿の量が減っている場合は病院で点滴治療が必要。
-
薬について:抗菌薬は重症例や免疫力が低い方に使われることがありますが、自己判断で服用するのは危険です。市販の下痢止めも使用は避けましょう。
受診の目安
-
・下痢が1日以上続く
-
・血便がある
-
・38℃以上の発熱がある
-
・嘔吐が止まらない
-
・脱水症状(強いだるさ、尿が少ない)が出ている
-
大田大森胃腸肛門内視鏡クリニックでは、症状や体調に応じた検査・治療を行い、早期回復をサポートしています。

4. 予防のためにできること
 カンピロバクターは「加熱」と「衛生管理」で防げます。
カンピロバクターは「加熱」と「衛生管理」で防げます。
-
・鶏肉は中心までしっかり火を通し、ピンク色が残らないように調理する。
-
・包丁・まな板・手を清潔に。肉と野菜で器具を分けるのが安心。
-
・外食時、「鶏刺し」「たたき」など生や半生の料理は感染リスクがあると理解して選ぶ。
-
・子ども、高齢者、妊娠中の方は特に注意。
毎日のちょっとした工夫で、食卓の安全は守れます。
5. まとめ|正しい知識で食中毒を防ごう
カンピロバクターは身近な食材から感染しますが、正しい調理と衛生管理で十分に防ぐことができます。
もし腹痛や下痢が続くときは「食中毒かも」と疑い、早めの受診が大切です。
大田大森胃腸肛門内視鏡クリニックでは、食中毒を含む胃腸疾患の診療・予防に力を入れています。
気になる症状があるときは、お気軽にご相談ください。
監修医師 大柄 貴寛
国立弘前大学医学部 卒業。青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、日本屈指の高度な専門施設、クリニックで消化器内視鏡・外科手術治療を習得後、2020年10月大田大森胃腸肛門内視鏡クリニック開院、2024年12月東京新宿胃腸肛門内視鏡・鼠径ヘルニア日帰り手術RENA CLINIC開院。



















