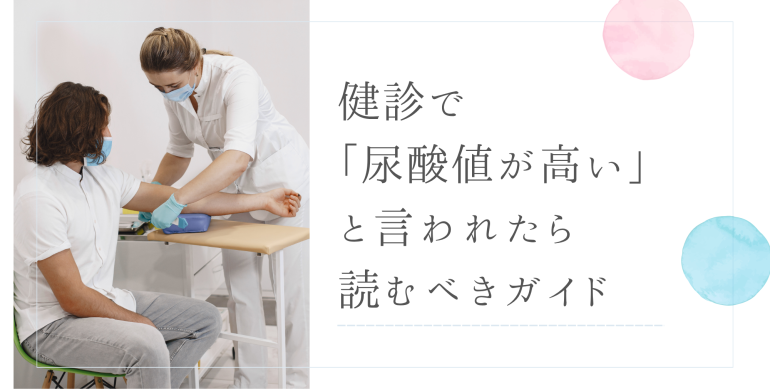
健康診断で「尿酸値が高いですね」と言われても、痛みや違和感がなければ「放っておいても大丈夫かな」と思ってしまう方は少なくありません。
しかし、尿酸値が高い状態=高尿酸血症は、放置すると痛風発作・腎臓の障害・尿路結石など、生活の質を大きく損なう病気につながる可能性があります。
本記事では、高尿酸血症の基準や症状、放置した場合のリスク、治療方法や予防策まで、医師の立場から詳しく解説します。
健診で尿酸値が高いと言われた方は、ぜひ参考にしてください。
1. 高尿酸血症とは?基準と種類
 高尿酸血症とは、血液中の尿酸が基準値を超えている状態を指します。一般的には尿酸値7.0mg/dL以上が診断の目安とされます。
高尿酸血症とは、血液中の尿酸が基準値を超えている状態を指します。一般的には尿酸値7.0mg/dL以上が診断の目安とされます。
尿酸は、体内で「プリン体」という物質を分解する際に作られる老廃物で、通常は腎臓を通して尿に排泄されます。しかし、尿酸が過剰に作られるか、排泄がうまくいかないと血液中にたまり、高尿酸血症になります。
高尿酸血症には次のタイプがあります:
-
・産生過剰型:プリン体を多く摂取する、あるいは体内での生成量が多いタイプ
-
・排泄低下型:腎臓から尿酸を排出する力が弱っているタイプ
-
・混合型:上記2つの要因が重なったタイプ
また、「無症候性高尿酸血症」と呼ばれる段階もあります。症状はないものの、この時点から生活習慣を見直すことで将来の痛風や腎障害を予防できます。
2. 高尿酸血症の症状と放置したときのリスク
初期の高尿酸血症は症状がほとんどなく、気づきにくいのが特徴です。ですが、尿酸が結晶となって関節や腎臓に沈着すると、以下のような問題が起こります。
代表的な症状
-
・突然の激痛を伴う「痛風発作」(特に足の親指に多い)
-
・関節の赤み・腫れ・熱感
-
・発作を繰り返すと関節の動きが悪くなる
放置した場合に起こる合併症
-
尿路結石:排尿時に激痛を伴う
-
腎障害・慢性腎臓病:長期的に腎臓の働きを弱める
-
痛風結節:関節や皮下にしこりができる
-
生活の質の低下:歩行困難や日常生活の制限につながる
「症状がないから大丈夫」と思っている間に進行しているケースもあるため、早めの検査と対策が重要です。
3. 診断と治療の流れ
高尿酸血症が疑われる場合は、以下の流れで診断・治療を進めます。
診断
-
血液検査:血清尿酸値の測定(7.0mg/dL以上が目安)
-
尿検査:尿酸排泄量を調べてタイプを分類
-
必要に応じて画像検査(結石や腎障害の有無を確認)
治療
-
生活習慣の改善:プリン体やアルコールを控える、十分な水分摂取、運動、体重管理
-
薬物療法:生活改善だけでは下がらない場合や合併症がある場合に使用(尿酸生成抑制薬、尿酸排泄促進薬など)
-
発作時の対応:痛風発作が起きた場合は炎症を抑える治療を行い、その後に尿酸コントロールを開始
治療のゴールは、尿酸値を6.0mg/dL以下に維持することとされています。
4. 日常でできる予防と生活習慣の見直し
 高尿酸血症の予防・再発防止には生活改善が不可欠です。
高尿酸血症の予防・再発防止には生活改善が不可欠です。
-
食事:レバー・干物・魚卵・甲殻類などプリン体の多い食材を控える
-
飲酒:ビールや日本酒は尿酸を上げやすいため制限を
-
水分摂取:1日2リットルを目安にしっかり飲む
-
運動:無理のない有酸素運動を習慣化
-
体重管理:肥満傾向がある場合は減量が効果的
5. 治療後のケアと長期管理
 高尿酸血症は一度治療しても、再び尿酸値が上がることがあります。
高尿酸血症は一度治療しても、再び尿酸値が上がることがあります。
そのため継続的なケアが欠かせません。
-
・定期的な血液検査で尿酸値をチェック
-
・腎機能や尿路結石の有無をモニタリング
-
・発作の前兆を感じたら早めに対応
-
・薬は自己判断で中止せず、医師と相談して調整
まとめ
高尿酸血症は「症状がないから大丈夫」と放置されがちですが、その先には痛風や腎障害といった深刻な合併症が待っています。
健診で尿酸値が高いと指摘された方は、早めに生活習慣を見直すこと、必要に応じて治療を受けることが将来の健康を守るカギです。
大田大森胃腸肛門内視鏡クリニックでは、診断から治療・予防まで一人ひとりに合わせたサポートを行っています。
気になる方はぜひご相談ください。
監修医師 大柄 貴寛
国立弘前大学医学部 卒業。青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、日本屈指の高度な専門施設、クリニックで消化器内視鏡・外科手術治療を習得後、2020年10月大田大森胃腸肛門内視鏡クリニック開院、2024年12月東京新宿胃腸肛門内視鏡・鼠径ヘルニア日帰り手術RENA CLINIC開院。




















