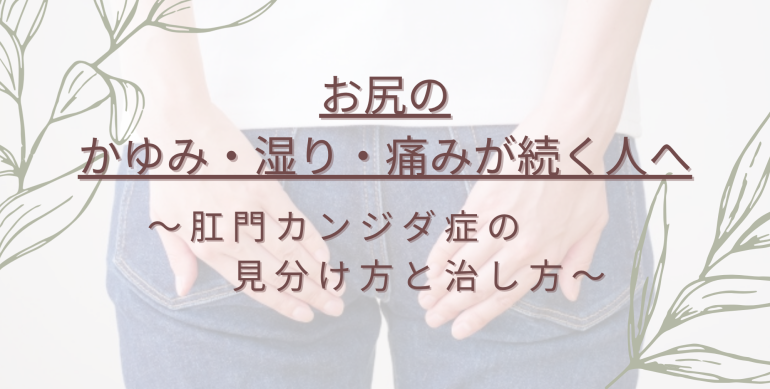
「なんだかお尻がかゆい」「拭いてもムズムズが取れない」──そんなとき、単なる“痔”だと思っていませんか?
実はその症状、肛門カンジダ症が原因のことがあります。
肛門カンジダ症とは、**カンジダ属菌(Candida)**という真菌(カビの一種)が肛門周囲で異常に増殖することで起こる感染症です。カンジダ菌は私たちの皮膚や腸内にも常に存在する常在菌ですが、汗や蒸れ、免疫力の低下などがきっかけで増えすぎると、かゆみ・痛み・湿りなどの不快な症状を引き起こします。
放置すると悪化して皮膚がただれたり、何度も再発したりすることもあるため、早めの受診が大切です。この記事では、原因・症状・治療法・予防のコツまでわかりやすく解説します。
1. 肛門カンジダ症の原因と発症しやすい状況
カンジダ菌が増えやすくなるのは、次のような環境です。
-
・肛門まわりが高温多湿の状態(汗をかいたまま、蒸れやすい下着やナプキンの使用など)
-
・清潔が保たれていない(排便後の拭き残しや洗浄不足)
-
・免疫力の低下(疲れ・睡眠不足・ストレス・糖尿病など)
-
・抗生物質やステロイド薬の使用(常在菌バランスの乱れ)
特に、汗をかきやすい季節や長時間座る仕事・運動後のケア不足は要注意です。
「蒸れる」「少しかゆい」といった軽い違和感も、早期発見のヒントになります。
2. 肛門カンジダ症の主な症状と見分け方
症状は人によって異なりますが、次のようなサインが特徴的です。
-
・かゆみ・ヒリヒリ感:排便後や入浴後に強くなる
-
・赤みや発疹、水ぶくれ:皮膚が湿ったように見えることも
-
・痛みや灼熱感:下着の擦れで痛みが出る場合も
-
・びらん・出血:進行すると皮膚が破れたり化膿したり
痔との違いは「湿り・かゆみ・水ぶくれ」。
痔では出血やしこりが目立ちますが、カンジダ症ではかゆみや湿った違和感が中心です。
特に「抗生物質を使った後に悪化」「汗や湿気で強くなる」という方は、カンジダ症の可能性があります。
3. 検査と治療の流れ
病院では以下のように診断・治療が行われます。
-
・問診・視診:症状の経過、生活習慣、発疹の有無を確認
-
・培養検査:皮膚のサンプルを採取し、カンジダ菌の有無を調べる
-
・除外診断:痔・裂肛・性病など他の疾患との見分け
治療は、
-
・**外用抗真菌薬(クリーム・軟膏)**を塗布
-
・改善しにくい場合は内服薬を併用
-
・患部の清潔保持と蒸れ防止を徹底
軽症なら1〜2週間で改善することもありますが、再発や広範囲の場合は長期治療が必要です。
薬の使い方や期間は医師の指示に従いましょう。
4. 再発を防ぐための生活習慣
 肛門カンジダ症は一度治っても再発しやすい病気です。
肛門カンジダ症は一度治っても再発しやすい病気です。
再発予防のために以下の工夫を取り入れましょう。
-
💡 通気性の良い綿素材の下着を選ぶ
-
💡 汗をかいたらすぐ拭き、下着をこまめに交換
-
💡 排便後はぬるま湯で優しく洗浄し、湿ったまま放置しない
-
💡 睡眠・栄養・ストレス管理で免疫力を維持
-
💡 抗生物質・ステロイド薬を使うときは医師と相談
こうした日常のケアが、再発の防止につながります。
5. 治療後のケアで快適に過ごす
治療後も油断せず、次のポイントを意識しましょう。
-
トイレ後は優しくケア:強くこすらず、やわらかい紙や洗浄機能を活用
-
通気性の確保:締め付けない下着・衣類を選ぶ
-
刺激物を避ける:熱いお湯・強い石鹸・香料入り製品は控える
-
生活リズムの改善:睡眠と栄養を整え、再発リスクを減らす
これらを続けることで、肛門周辺の環境が整い、再発の頻度を減らすことができます。
まとめ
肛門カンジダ症は、「かゆみ」「湿り」「ヒリヒリ感」などの軽い違和感から始まります。
放置すると悪化し、生活の質を大きく損なうこともあります。
早期発見と正しい治療、そして生活改善が何より大切です。
大田大森胃腸肛門内視鏡クリニックでは、専門的な検査・治療から再発予防まで一貫してサポートしています。
「お尻のかゆみや違和感が続く」という方は、我慢せず早めにご相談ください。
監修医師 大柄 貴寛
国立弘前大学医学部 卒業。青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、日本屈指の高度な専門施設、クリニックで消化器内視鏡・外科手術治療を習得後、2020年10月大田大森胃腸肛門内視鏡クリニック開院、2024年12月東京新宿胃腸肛門内視鏡・鼠径ヘルニア日帰り手術RENA CLINIC開院。




















